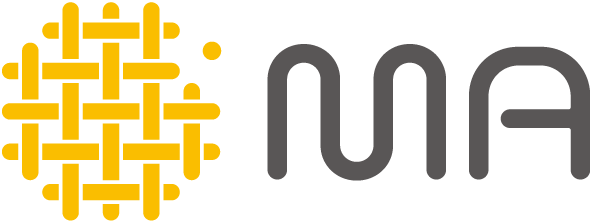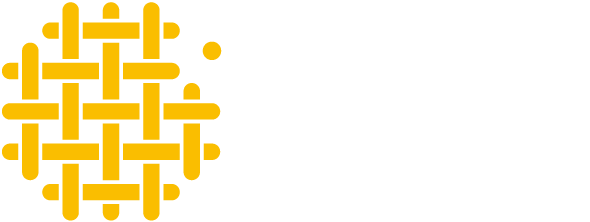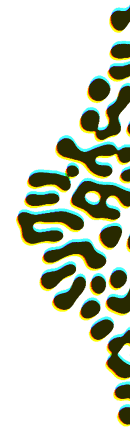「展示会がゴール」──成果物を“見せる”ハッカソンという形 〜テックシーカー2025の事例〜

「新しいビジネスに結びつけたい」「サービスを多くの人に知ってほしい」「参加者が“やってよかった”と思えるイベントにしたい」そんな想いを持つ担当者の皆様にとって、“展示会をゴールに据えたハッカソン”の事例は、参考になるかもしれません。
<事例要約>
✔ハッカソンのゴールは、開かれた「展示会」で市民にも触ってもらう場
✔ハッカソンは多様な参加者と共に共創体験ができる貴重なイベント
✔5000円チケットを配布し、電子部品を買いに行く時間が設けられた電子工作ハッカソン
担当の方に、抱えていた課題と、依頼してよかったことについてお伺いしました。
お伺いした会社:ソフト産業プラザTEQS さま

ハッカソンは「セミナーや研究会とは異色な挑戦の場」
Q:ハッカソンを開催している理由について教えてください
「ソフト産業プラザTEQSは、先端技術を活用した産業支援をしており、特にここ数年はテクノロジー企業関連の支援を中心に行っています。その活動の中で、セミナーや研究会、展示会といった”場の提供”を数多くしています。
セミナーは“Pythonを学びましょう”みたいにゴールが決まっていて、研究会は事例共有や情報交換の場として機能しています。セミナーや展示会だと、同じテーマに関心を持つ人しか集まらないんですが、ハッカソンは、学生も社会人も、ハード系の人もソフト系の人も、あらゆるジャンルの人が集まって、一同の場に集まる貴重な場だと認識しています。
また、集まるだけでなく、はじめましての人と短期間で一緒にプロトタイピングを作り上げていく体験は他のイベントにはないので、ここから新しいサービスが生まれると嬉しいなと思っています。」
そう語るのは、イベントや展示会なども手掛けているソフト産業プラザTEQSの加味さん。
人と人とをつなげる「場の提供」を多くする中で、ハッカソンは他のイベントにはない”多様性”があると同時に、普段接することのない人とチームを組むことで、新しい技術や知見を得たり、コミュニケーション力を養ったりなど、特別な”体験”があると語ってくれました。
イベントの進め方も時代に合わせて進化し、名物も生まれた
Q:MAに依頼してよかった点は、どんなところでしたか?
「展示会の運営イメージは過去の経験からありましたが、”成果をつくるプロセス”であるハッカソンの運営にはノウハウがなく、限られた予算の中で、ハッカソン運営のみを外部に委託しています。
実際にお願いすると、こちらがお願いする以上に、必要なことを次々と推進いただけるので安心してお任せでき、イベントの進め方も時代に合わせて進化(例:紙のアイデアシートからスプレットシートでのアイデア出し)しているので刺激にもなります。
また、”イベント中に実際の店舗に足を運んで中継しよう”といったアイデアも提案いただき、今では名物になっています。」
テックシーカーハッカソンの特徴の一つは、スポンサーである共立電子産業株式会社さんから参加者全員に、「電子パーツ購入チケット5000円分/人」が配布されることです。店舗からの部品紹介の中継の影響で、ハッカソン2日目の午前中に参加者の方が店舗にお買い物に行くのが、今では恒例となっています。
「エンジニアがどんなコトに食いつくか」「どんな瞬間にテンションが上がるか」――そんな現場感覚を活かして、企画から運営、演出まで一貫してご提案できるのがMAの強みです。
ここからは、ハッカソンの概要となります。
テーマは「AI活用〜AIで魔法の道具を作ろう!〜」
「テックシーカーハッカソン」は、プレゼンテーション&デモンストレーションでの優劣を競う競技ではなく、成果物の特長を評価して表彰するハッカソン。ハッカソンで終わりではなく、一般市民の方も参加される展示会で展示するところがゴールです。
また、スポンサーでもある共立電子産業株式会社さまから電子パーツ購入チケット5000円分/人が参加特典として配布される特徴をもっています。
ハッカソンは2018年に開催されたデジットハッカソンから継続され8回目の開催となり、展示会(旧:メイカーバザール)はもっと前からの歴史があります。
●日程:2025年7月〜8月
●イベント名:テックシーカーハッカソン
●主催:ソフト産業プラザTEQS(公益財団法人大阪産業局)、一般社団法人iRooBO Network Forum
●共催:咲州サテライト万博実行委員会
●運営協力:ProtoPedia(一般社団法人MA)、NPO法人 Code for OSAKA
●参加者:92名(16チーム)
内容(プログラム)
| Day1 | 1.アイデア出し 2.テクニカルインプット(スポンサー企業から提供されるサービス、APIの紹介) 3.チームビルディング(アイデアをもとに4,5名のチームを結成) 4.チームアイディエーション(チーム毎に成果物のイメージを固める) 5.エレショップからの中継(日本橋にある共立電子産業の店舗を動画でライブ中継) 6.製作予定物の発表 7.懇親会 |
| Day2 | 1.パーツ買い出し 2.中間発表(イメージする成果物についてプレゼンテーション) 3.ハッカソン(購入したパーツを組み上げる) |
| Day3 | 1.成果発表、デモの実施 2.審査&体験会 3.結果発表 |
| Day4,5 | 展示会(テックシーカーコレクション) |
場所
●会場:ATC特設会場(大阪)
●アイデア発散:Googleスプレッドシート
●コミュニケーション:Discord
つくったものを、市民に触ってもらう・見てもらう体験まで組み込まれたハッカソン
ハッカソンの特徴は以下のとおりです。
- 参加者全員に電子パーツ購入チケット5,000円/人を配布
スポンサーの共立電子産業株式会社から、参加者全員に電子パーツ購入チケット5000円/人を配布。イベント2日目の午前中は、参加者の多くがパーツの買い出しにいくため、会場の参加者はまばら。店舗でパーツをみてアイデアを思いつく流れもあり、技術の無駄遣い作品も多く生まれる。 - ハッカソンのゴールは展示会
閉じられたハッカソン場で審査員が優劣をつけるのではなく、展示会で展示し、多くの一般の方に触ってもらうこと・見てもらうのがゴール。一般的な市民に触ってもらうことで、マーケットとの接点も体感すると同時に、市民が最新テクノロジーに触れる場でもある。 - 開発時期が長い
アイデアソン・ハッカソンが2日間で開催され、発表・展示会までにおよそ1ヶ月超の開発期間が設けられている(2025年は万博の関係で発表と展示会が別日になりましたが、通常はプレゼン・展示会は同日) - 自由なモノづくりの場
審査員不在で「モノづくり」にフォーカスされた雰囲気があるためとても自由。そのことが初めてのハッカソンの場として、学生さんに心地よい体験を提供し、後輩を連れてくる循環がある。
おわりに
今回のように、「展示をゴールに据えたハッカソン」は、閉じられた場でつくられ発表するハッカソンとは違い、参加者の方にとって多くのフィードバックがもらえると同時に、作品に利用されたサービスも多くの人に知ってもらえる機会となります。
自社で展示会まで企画することはハードですが、既存の展示会と接続する形でハッカソンを企画・設計することも可能ですので、そんなハッカソンにご興味がある方は是非ご相談ください。
<関連リンク>
・テックシーカーハッカソン2025(ハッカソン公式ページ)
・ハッカソン作品一覧|ProtoPedia
・様々な魔法道具が生まれた「AI×電子工作ハッカソン」 |ブログ
その他の事例
-
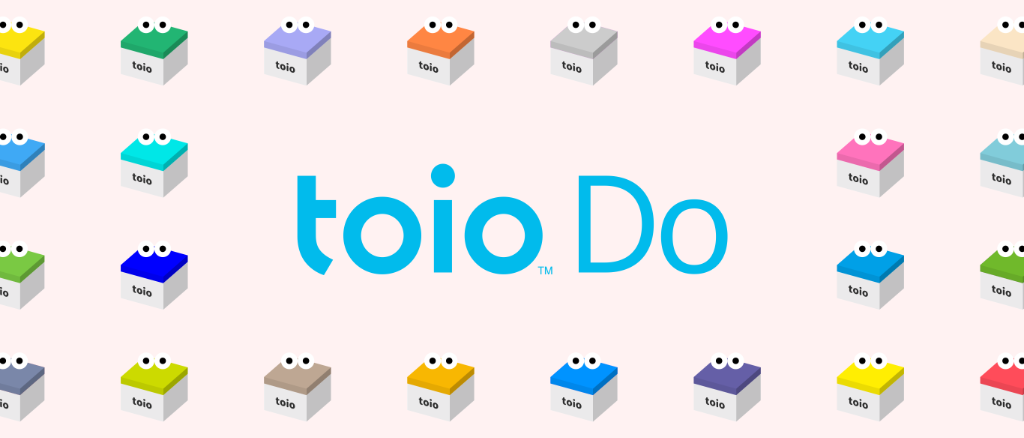
デバイスを配布し、サンプルプログラミングを募集したtoioの「Do!コン」
#ProtoPedia #コンテスト #オープンイノベーション -
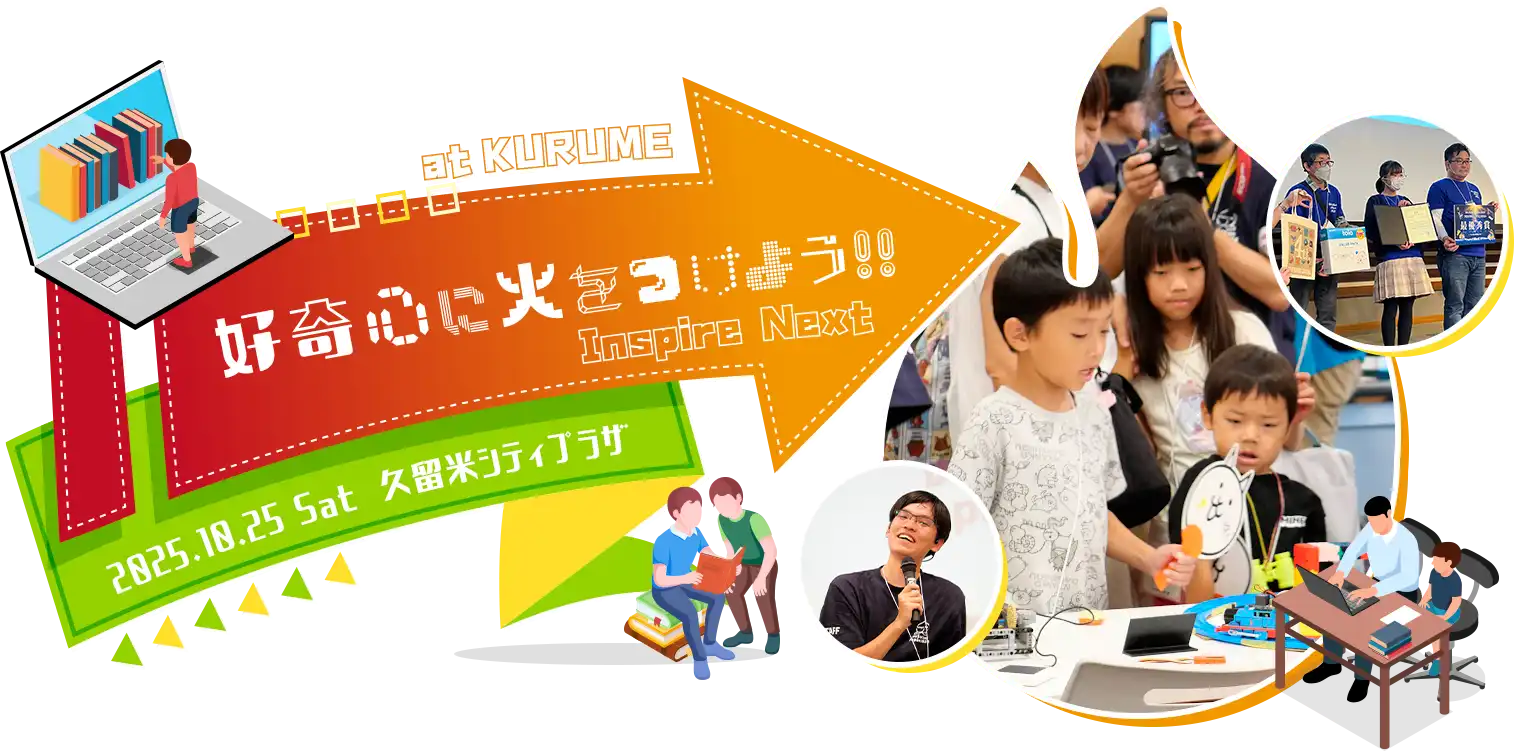
初運営の不安を払拭し、28作品すべてを輝かせたDojoCon Japan 2025プログラミングコンテストの事例
#ProtoPedia #コンテスト -

多拠点で同時開催した「NRIハッカソン bit.Connect」
#ProtoPedia #ハッカソン #社内ハッカソン #オープンイノベーション -

メイカーのものづくり魂を刺激した「Mouser Make Awards2023」
#ProtoPedia #コンテスト #オープンイノベーション